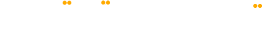平和を守るためには何もしないという日本憲法を前提に、北や中国はミサイルや謀略で脅してくる。
何もしない日本をいつまで続ける?
国民に自衛権がない日本
米国の政変、中国の謀略、そして北朝鮮のミサイル
平和憲法という勘違いから目覚める
喫緊の事態が迫っている
しかし憲法第9条には、平和を守るためには
何もしない、と書いてあるのだから
日本国憲法は、むしろ「平和がいらない憲法」
と言った方が正しいのではないか?
自分で自分を守る権利さえ持てない日本人を
侵略から守るための17説を考える
平和いらない憲法
侵略されないための17説
天尾あきら
もくじ
プロローグ
ある友人の勘違いで、考えたこと
未だに続く「平和的な解決」
その時マスメディアは
人質救出が最優先事項ではない?
無知ゆえの非礼
第1説 抑止力ってなんですか?
軍事常識とは無縁な人々
掛け捨て保険みたいなもの?
軍国主義の国家とは?
軍事アレルギーが正常な感覚?
第2説 きちんと客観的に評価しよう
日本人の精神年齢は12歳
ポーカーを知らない日本人の外交
客観的な評価の欠落
中華料理は世界一
パンがなければケーキ?
第3説 歴史のロマンと現実と
日露戦争の定説を考える
ノモンハン事件の教訓
南京虐殺30万人という数字の根拠
対米戦の誤算と誤解
「礼節の国」の人々の正体
第4説 前の時代は悪かった
反省、反省、反省?
中高の授業で刷り込まれたこと
中国の謀略は反省の対象外?
第5説 価値観の違いとはどういうことか
日本人ってやっぱり特殊?
文化、そのバックグラウンドの違い
第6説 己を知ること、知らしめること
「日本人は顔が見えない」とは?
農耕民族の末裔の行方
価値観を自覚しない日本人
第7説 思考停止して真相から目をそらすな
ガンジーとインド人の決意
実は軍事攻撃されていた日本
「生きて虜囚の辱めを受けず」
第8説 戦争にもマナーがあった?!
死に対する畏敬の念
哀れなまでに正直な人たち
第9説 アジアの懸念とは何か?
新聞テレビのデタラメを放置してはならない 日本の不思議な良識 今でも尾を引く愚かな選択 仮想敵国とは?
第10説 ユダヤ人と日本人
ユダヤ人の覚悟とは 外交能力ゼロの日本の政治家 北方領土は戦利品ではない
第11説 平和いらない憲法
憲法9条と日米安保
「戦争」という差別概念
平和憲法という勘違い
フヌケ国家、媚びへつらい国家、泣き寝入り国家
話し合う? 何を?
第12説 非核三原則は原則にできない
広島、長崎の遺品展示の失敗
核に関する無知
第13説 日本は過剰防衛の国?
国民に自衛権がない日本
自衛権に噛みつく因子とは?
第14説 何が何でも必要最小限
これが日本人の美徳、日本人の弱点
必要最小限は当り前ではない
第15説 自衛隊は何のため?
♪兵隊さんは可哀想だね♪
消防団は軍隊ではない
自衛隊の任務は弁当の配布?
シビリアンコントロールで責任回避?
第16説 尖閣ビデオ隠しは国家犯罪だ
あきれる日本マスメディアの判断力
菅、仙谷は国家反逆罪で死刑!?
第17説 これはとっくに戦争だ
軍事常識がない人々の右往左往
迎合するマスメディアと政府の対応
平和認知症全体主義
大災害の軍事的考察
悲観的なエピローグ フヌケ、媚びへつらい、泣き寝入り国家の行方
危機の要因
中国、アメリカとの付き合い方
はたして神風は吹くか?
あとがき
著者について
天尾あきら 1949年生まれ。1971年、UHF千葉開局時、年齢を詐称して、ディレクターとして番組制作に従事。
1972年フリーディレクターとなり、番組制作、コマーシャル、PR映画、ビデオ等、幅広く手がける。
1990年代以降は、主として公共事業記録映画・ビデオの制作に携わるが、2009年、民主党政権発足後、レギュラーの仕事が次々と消滅。ほぼ失職状態となり、以後執筆活動に入る。